第4回
 つうと人魚姫が黎明へやって来てから約一年。血式少女隊は、早くも七人にまでその人数を増やしていた。
つうと人魚姫が黎明へやって来てから約一年。血式少女隊は、早くも七人にまでその人数を増やしていた。血式少女は正確な年齢が不明である。だが成長の度合いからおおよその年齢を推し量ることはできるので、黎明では暫定的に血式少女の年齢を決めている。
それによると、現時点で最年長は11才の赤ずきん。その下に9才のシンデレラ、6才のつう、人魚姫と続き、一番下が、5才の親指姫、白雪姫、眠り姫。黎明へ来たばかりの、三つ子の三姉妹である。
三姉妹はもともと解放地区にある孤児院で保護されていた。その保護者から黎明のメンバーへ、子供たちを拾ったときに目がピンク色に光っていた、と報告が入り、黎明はすぐに孤児院を訪れ、血式少女だと確認されたその子供たちを引き取った。
それが三つ子の三姉妹であったことは、黎明にとっては望外の幸運だったと言える。血式少女は対メルヒェン用の切り札だ。何人いても困ることはない。
博士はその時、血式少女は最低七人必要だ、と考えていた。
ジェイルには監獄塔を中心に七つの独房エリアがある。
その独房エリアのひとつひとつに『核』があり、それがメルヒェンを生みだしている。その核をすべて破壊し、ジェイルから独房エリアに供給されている栄養を監獄塔に集中させることによって塔を成長させ、天幕を破ることが血式少女隊の最終目的である。
調査の結果、各独房エリアにはメルヒェンよりも恐ろしい不死身の化け物、ナイトメアが存在することが分かっている。このナイトメアを倒すはっきりとした方法はいまだ不明であるが、博士は、血式少女なら刺し違えることは出来るのではないか、と考えている。
そのため、一つの独房エリアにつき一人。最低七人の血式少女が――その犠牲が、必要なのではないかと。
とはいえ。
「血式少女隊。思ったり早く、七人揃いましたね」
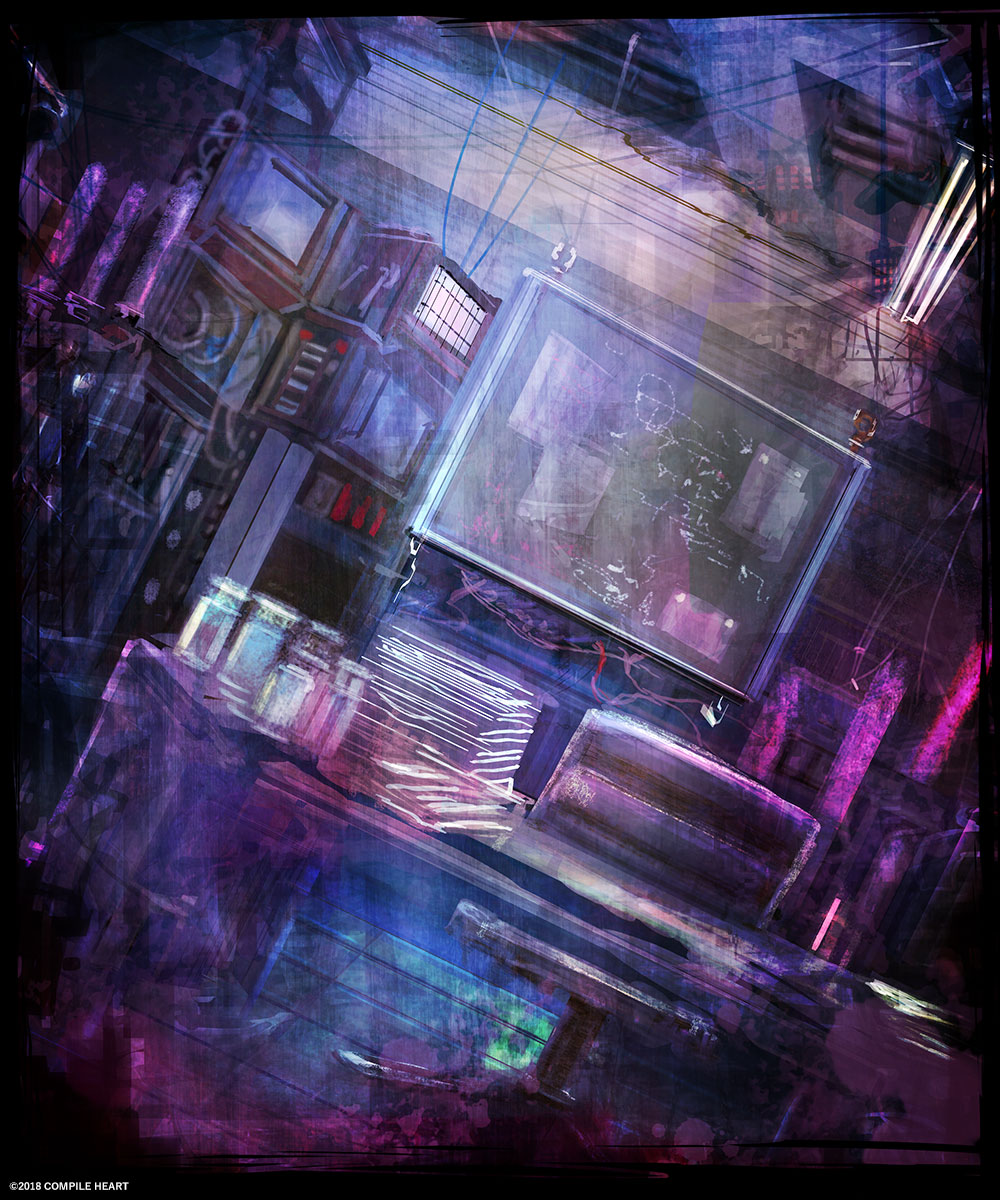 静かな研究室に、眼鏡をかけた白衣の女性、視子の声が響く。救護班の班長であり、血式少女の体調管理なども手がけているため、ある意味黎明で最も血式少女たちをよく知る人物だ。
静かな研究室に、眼鏡をかけた白衣の女性、視子の声が響く。救護班の班長であり、血式少女の体調管理なども手がけているため、ある意味黎明で最も血式少女たちをよく知る人物だ。視子の声は、血式少女が増えたことを喜ぶような様子はなく、むしろ話しかけた相手、博士をやや責めるような冷徹なものだ。
それを聞いた博士は、苦笑しながら視子に顔を向ける。「そう怖い声を出さないでくれたまえ視子くん。分かっているよ、あの子たちはまだあまりにも幼い。無理をさせるつもりはないさ。もちろん犠牲が出ないに越したことはない。そのためにも、しばらくは研究と実験を続けないとね……何しろ、血式少女たちについては分からないことが多すぎる……」
そう言って目を向ける机の上には、血式少女たちから採取した血液サンプルとその分析結果を記した紙が並んでいる。
「いずれ、本格的な戦いが始まる。せめてそれまでは、あの子たちをなるべく普通の子供のように育ててやってほしい。視子くんのことは頼りにしているよ。同じ女性でないと気が回らないこともあるだろうからね」
「……はい」
苦々しく頷く視子。まだ幼い少女たちに、人類の希望というあまりにも大きなものを背負わせようとしていることを、黎明の人間たちは誰もが心苦しく思っていた。
「……それはそうと博士、例の孤児院のことですが」
「うん? どうかしたかね」
「どうも、本格的に宗教じみてきたようです。ミチルという虹彩異色症の少女を、何者かが『大陽女』などと呼んで教祖に仕立て上げているみたいですね」
「ふむ……」
「その弟、千昭という少年は自らを『陽司』と名乗り、大陽女の側近的な立場を取っているようです。どちらもまだ子供ですから、自覚しているかどうかはともかく、誰かに何らかの目的で利用されているのではないでしょうか」
「何か、具体的な問題が出ているのかね?」
「いえ、それは今のところ。活動自体は今まで通りで、たまにミチルがお告げのようなものをするだけのようです」
「なるほど……それなら、しばらくは様子見でいいのではないかね? 孤児院の活動にはこちらも随分助けられている。人々には黎明だけでなく、あちらも必要だよ」
「はい……それはまぁ、いいんですけど。一つだけ気になることが」
「と言うと?」
「三姉妹です。あの子たちはもともとミチルや千昭と仲が良かったらしく、今でも孤児院……今は『タイヨウ教団』と呼ぶらしいですが、そこへ遊びに行っています」
「まぁ、そのくらいはいいじゃないか」
「ですが、最近では年の近い子たちも一緒について行っているみたいで……ミチルは今、教団内で神聖視されているようですし、将来的に何か問題の種になるかもしれません」
「ふむ……」 視子の話を聞き終えた博士は、考え込むように顎に手を当てる。
「年の近い子、というと……」
「つうと、人魚姫です」
◯ つうと人魚姫は、最初は血式少女隊の最年少だった。だが三姉妹がやって来たことにより、ひとつお姉さんという立場になった。正確な年齢は分からないが、おそらく三姉妹が一つくらい年下だろうということだった。
妹が出来て嬉しくなったつうたちは、赤ずきんやシンデレラよりも三姉妹と遊ぶことが多くなった。そして三姉妹は、つうと人魚姫を自分たちのいた孤児院に連れて行き、仲の良いミチルと千昭に紹介した。
初めてミチルに会ったとき、つうは驚いた。
「君……目の色が……!」
「わぁ……あなた、わたしとおんなじ目をしてるのね」
つうの目は、右が赤、左が青という左右で違う色をしていた。つうは、人魚姫に「とっても綺麗な目の色ね」
と教えられて初めてそれを知り、人魚姫に褒められた自分の目の色を気に入っていた。だから、同じ目の色をしたミチルに会って驚いたのだ。
もちろん、驚いたのはつうだけではない。他の血式少女たちも、そして千昭も驚いている。
「姉さんと同じ目の人がいるなんて……」
「うふふ。嬉しいなぁ。わたしはミチルっていうの。こっちは弟の千昭。あなたは?」
「あ、僕はつう。それでこっちが」
「人魚姫です。よろしくお願いします」
「つうに、人魚姫……そっかぁ、あなたたちも、そうなんだね」
どこか夢見るような口調でぼんやりと話すミチル。今までに話したことのないタイプで、つうと人魚姫はリアクションに困ってしまう。
「……あれ? でも、あなたは……」
するとミチルは首を傾げ、何故か突然つうを抱きしめた。
 「えっ!?」
「えっ!?」「なっ……!」
驚くつうと絶句する人魚姫。ミチルは気にした風もなく、つうの髪に鼻先をうずめる。
「くんくん……」
「ちょ、ちょっと、はなして——」
ミチルを手で押しのけようとして、つうの動きが止まった。
(……あれ?)
つうの脳内に、何か不思議な感覚がある。
(なんだろう、この感じ……この人……?)
黙って抱き合う形になっている二人。やがてミチルが顔を上げ、つうの顔をのぞき込む。
「あなた——」
「だ、だめー!」
大きな声と共に二人を引き離したのは、人魚姫だった。
「ひ、姫!?」
「おつうちゃんは、私の王子さまなんだから!」
人魚姫の叫びを聞いて、目を丸くするミチルと千昭。あまりつうと仲良くしていると人魚姫が嫉妬することをすでに知っていた三姉妹は、慌てて人魚姫をなだめようとする。
「お、落ち着いて人魚姫! ミチルはつうを取ったりしないから!」
「そうですよ! ミチルお姉様はとっても優しいんです!」
「ん……ん……!」
はっと我に返り、顔を赤くする人魚姫。ごめんなさい、と頭を下げたところで、ミチルが明るく笑い出した。
「うふふっ、あはははっ。そっか、つうは人魚姫の王子さまなんだ。人魚姫は王子さまと結ばれたんだね。素敵だね」
その笑顔が、本当に優しそうで、嬉しそうで。
つうも人魚姫も、しばしミチルに見惚れてしまった。
「じゃあさ、みんなで遊ぼうよ! いいでしょ、ちー?」
「うん、そうだね。これだけ人数がいるといろいろと遊べそうだ。何をしようか」
千昭は木の枝を拾って地面に何かを書き始める。どうも姉よりも弟の方がしっかりしていそうだな、という印象をつうたちは受けた。
何をして遊ぶかが決まって、チーム分けをしているとき、千昭がそっとつうに近づいてきて、ぽんと肩を叩いて耳元に囁いた。
「つう、これからよろしく。お互い大変だけど、何かあったらなんでも相談してくれ」
「え? うん、分かったよ。ありがとう」
どうして千昭が自分にだけそんなことを言うのか、その時のつうには分からなかったが、千昭の声が優しかったので嬉しそうに頷く。
後に、この時の千昭はつうを男だと思い込んでいたことが判明し、つうは『王子さま』として喜んでいいやら『血式少女』として悲しんでいいやら、何だかとても複雑な気持ちになったという。
◯ 「準備が出来たら、ケージの中へお入り」
「はい」
ある日の研究室。
実験用の衣服に着替えたつうは、言われた通りにケージの中へと歩を進めた。
実験が好きな血式少女などいない。だが、それが自分たちのやるべきことなのだと納得はしている。まるで自分が動物になったような気分でケージの外を眺めながら、つうは博士の指示を待った。
ケージの中には金属製の棚が置いてあり、その上にピンク色の液体で満たされた試験管が何本か置いてある。中身はいつもの通り、メルヒェンの血だろう。
「では始めよう。まず、一番の血を舐めなさい」
メルヒェンの血を舐める、ということが最初は気持ち悪かったが、もうすっかり慣れてしまった。それに、メルヒェンの血は甘くておいしいのだ。甘いものなど滅多に食べられないので、最近では少し楽しみになっているくらいである。
言われた通りに血を舐める。体が昂揚する感覚。おそらく、自分の目は今ピンク色に染まっているのだろう。つうはぼんやりとそんなことを考える。
いつもなら血を舐めた後はいろいろとやらされるのだが、今日は何も言われなかったのでつうはただその場に立っているだけだった。
「……よし。では次、二番の血を舐めなさい」
結局何もしないまま、次の指示が出る。その通りに二番の試験管を手に取るつう。
(……あれ?)
その血を口に近づけた瞬間、何か、さっきと違う感じがした。
(なんだろう? 匂いが違う? なんだか、こっちは……)
疑問に思いながらも、その血を舐める。体が昂揚する感覚は同じだ。だが。
(この感じ……どこかで……)
自分の体が、何かに反応しているのを感じる。
これは、この感覚は、知っている気がする、これは確か——
「……あ」
そして、つうはそれを思い出した。 ◯
 「珍しいね、二人だけで会いたいなんて」
「珍しいね、二人だけで会いたいなんて」三日後。孤児院の裏で、つうは千昭と会っていた。
つうを男だと思っていた千昭は、同じ男同士ということで、つうに特別良くしてくれていた。つうが女性だと分かった後も、あからさまに態度を変えることもなく、頼れる兄であり続けてくれた。
だからつうは、千昭に相談することにした。
先日、実験で謎の血を舐めたとき。
ミチルに抱きしめられたときと、同じ感覚を覚えたことを。
連載第5回は、5月24日発売の電撃PlayStation® Vol.663に掲載