 メアリーは、それはもうすごい勢いでシャーロットに懐いた。
メアリーは、それはもうすごい勢いでシャーロットに懐いた。「なぁなぁシャーロット、い、い、一緒に寝ようぜ!」
「なんか頭いてーんだよなぁ……なでなでしてくれたら治るかもなぁ……」
「あ、ああ、あーんってしてくれよ……へへ……」
一事が万事、この調子である。
メアリーからしてみれば、よく妄想した『無条件に優しく甘やかしてくれる美人の巨乳お姉さん』がいきなり目の前に現れたのだ。ここぞとばかりに妄想の中でやっていたことを実行してしまう。しかしシャーロットはそんなメアリーを優しく受け入れ、時に叱りつつも、最後には笑顔で許してしまうのだった。
さすがに申し訳なくなったのか、ある日メアリーは唐突に、こんなことを言い出した。
「服、作ってやるよ」
目をぱちくりとさせるシャーロット。
この街の人々にとって、服とはただ着るだけの物で、お洒落などは縁のない概念だ。シャーロットも質素でみすぼらしい服装をしている。
一方、何故かメアリーは、しっかりした個性的な衣装を身につけていた。
「メアリー、服なんて作れるの?」
「おう、俺のこの服だって自分で作ったんだぜ?」
人には見かけによらない特技があるものだ。シャーロットは感心し、そういうことなら、とありがたく申し出を受け入れる。
そうしてメアリーがシャーロットを連れて行ったのは、とある独房エリアの中心部、黎明の人間が『核』と呼んでいる物体がある部屋だった。
誰にも気づかれないメアリーの特性と、シャーロットの『見える』能力で、二人は上手くメルヒェンを避けながらそこへ辿り着く。
こんなところでどうやって服を? と訝るシャーロットの目の前で、メアリーは一本のマッチを擦り、それを核に投げ入れた。
マッチの炎を飲み込んだ核は、怪しく光り、蠢き、やがて何かを産み出す。
「……よし、一丁あがりっと」
それは確かに、一揃えの衣服だった。
「メアリー……あなた今、何をしたの……?」
「へへっ、すげーだろ。こいつさ、俺が妄想しながらマッチを擦って放り込んだら、その通りの物を作ってくれるんだぜ」
得意げに胸を張るメアリー。褒めてほしそうにちらちらとシャーロットを見ている。
だが、シャーロットはそれどころではなかった。
(妄想を、具現化する能力……? そんなの普通の人間にできるわけがない。やっぱりメアリーは血式少女なの? だとしたら――)
マッチ売りの少女は、ある寒い冬の夜、売れないマッチを擦りながら幸せな幻を見て、最後のマッチが燃え尽きたとき、誰にも気づかれずに凍えて死んでしまう。
「メアリー! マッチの無駄遣いをしては駄目! 死んでしまうわよ!」
シャーロットは、はっきりとその結末を『見て』しまった。妄想の代償にしては酷すぎる。絶対に現実にするわけにはいかない。
「な、なんだよ……怖い顔して……」
驚きうろたえるメアリーに、シャーロットは理由を説明する。しかし、それを聞いてもメアリーは今ひとつピンと来ていない様子だ。
「幸せな幻を見ながら死ねるんだったら、別にいいけどな……」
「そんなことを言わないで……お願い」
悲しそうに、シャーロットはメアリーをぎゅっと抱きしめる。また別の孤独を抱えていたシャーロットにとって、メアリーはもう、本当の妹のような存在だった。
メアリーは「分かったよ」と頷きながらも、押しつけられた胸のやわらかさを堪能することに夢中だった。クズである。
その後、せっかくなので作った服は着ることになったのだが。
「……メアリー? この服、胸が半分出てるんだけど……」
頬を赤らめてメアリーを睨むシャーロット。
「あ、あれ~? 失敗したかな? で、でも、貴重なマッチで作った服だしなぁ……捨てるのも作り直すのももったいないし、そのまま着るしかないな! ぐへへ!」
邪悪な顔が、明らかにわざとであることを物語っていた。
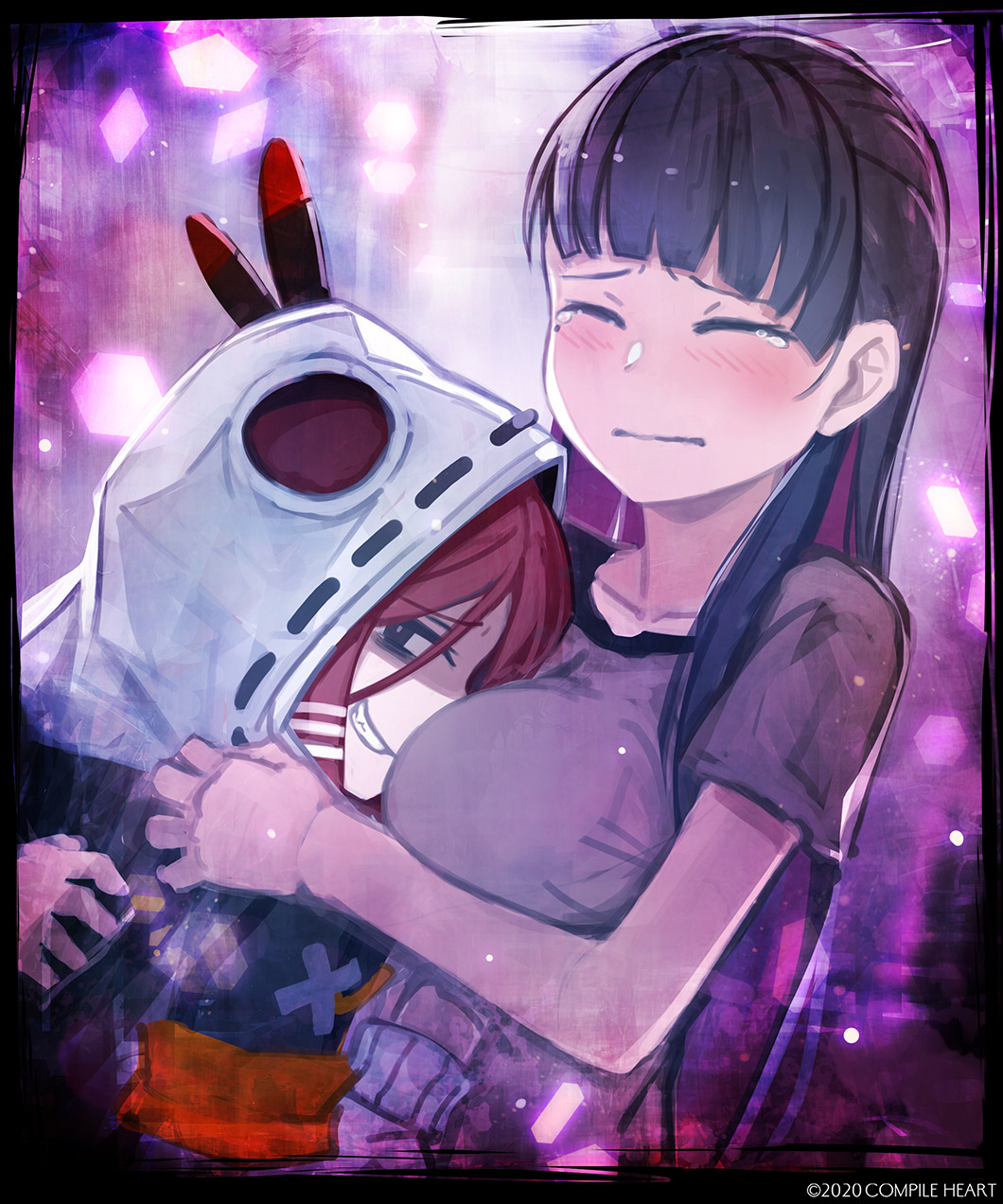 ◯
油断していた。
◯
油断していた。「……うわあっ!?」
いつの間にか、シャーロットの背後に一匹の小さなメルヒェンがいた。
「な、な、なんだお前! どっか行けよ!」
驚いて思わず蹴飛ばしてしまうメアリー。メルヒェンはさすがにその存在に気づき、襲いかかってくる。
「メアリー!」
シャーロットは咄嗟に大きな石を拾い上げ、反射的にメルヒェンを殴りつけた。
『グギャアッ!』
飛び散った血が二人にかかる。その一撃でメルヒェンは戦意を喪失したようで、あっさりと逃げていった。
「メアリー、大丈夫……!?」
無事を確認しようとして、シャーロットの言葉が止まった。
メルヒェンの血を浴びたメアリーの瞳が、ピンク色に光っている。
「あなた、やっぱり……」
「うおぉっ!?」
シャーロットの驚きは、さらに大きな声にかき消された。
「シャ、シャーロット! なんだそれ!? 目がピンクだぞ!?」
「え!?」
二人は近くに転がっていた鏡をのぞき込み、自分達の目の色を確認する。
「えっ、俺も!? マジかよ怖ぇ! なんかの病気じゃねぇだろーな! あ、でも待てよ、よく考えたらかっこいいかも!? 魔眼か? 俺は魔眼の持ち主だったのか!?」
妙に前向きに混乱するメアリーの言葉も耳に入らず、シャーロットは呆然と呟く。
「私も……血式少女だった……?」
 ◯
自分もメアリーも血式少女だと知ったシャーロットは、悩んでいた。
◯
自分もメアリーも血式少女だと知ったシャーロットは、悩んでいた。私たちは、黎明へ行くべきだろうか?
いや、メアリーはきっとそれを嫌がるだろう。私だって、あの子たちみたいに戦えるわけじゃない。それに何より――
行けば、当事者になってしまうかもしれない。
自分は傍観者だ。名前のない脇役だ。ずけずけと物語に踏み込んではいけない……。
半ば言い訳のように自分に言い聞かせながら、シャーロットはメアリーと二人、黎明には行かず今までのように暮らすことを決めた。
それから間もなく、物語には新たな登場人物が現れる。
アリスとジャック。
二人の登場により一気に動き始めた血式少女たちの脱獄劇を、シャーロットは瞼の裏で見守り続けた。ずっと、傍観者であり続けた。
そしてついに、人々がこの地下監獄から地上へと脱出するときがやってきた。